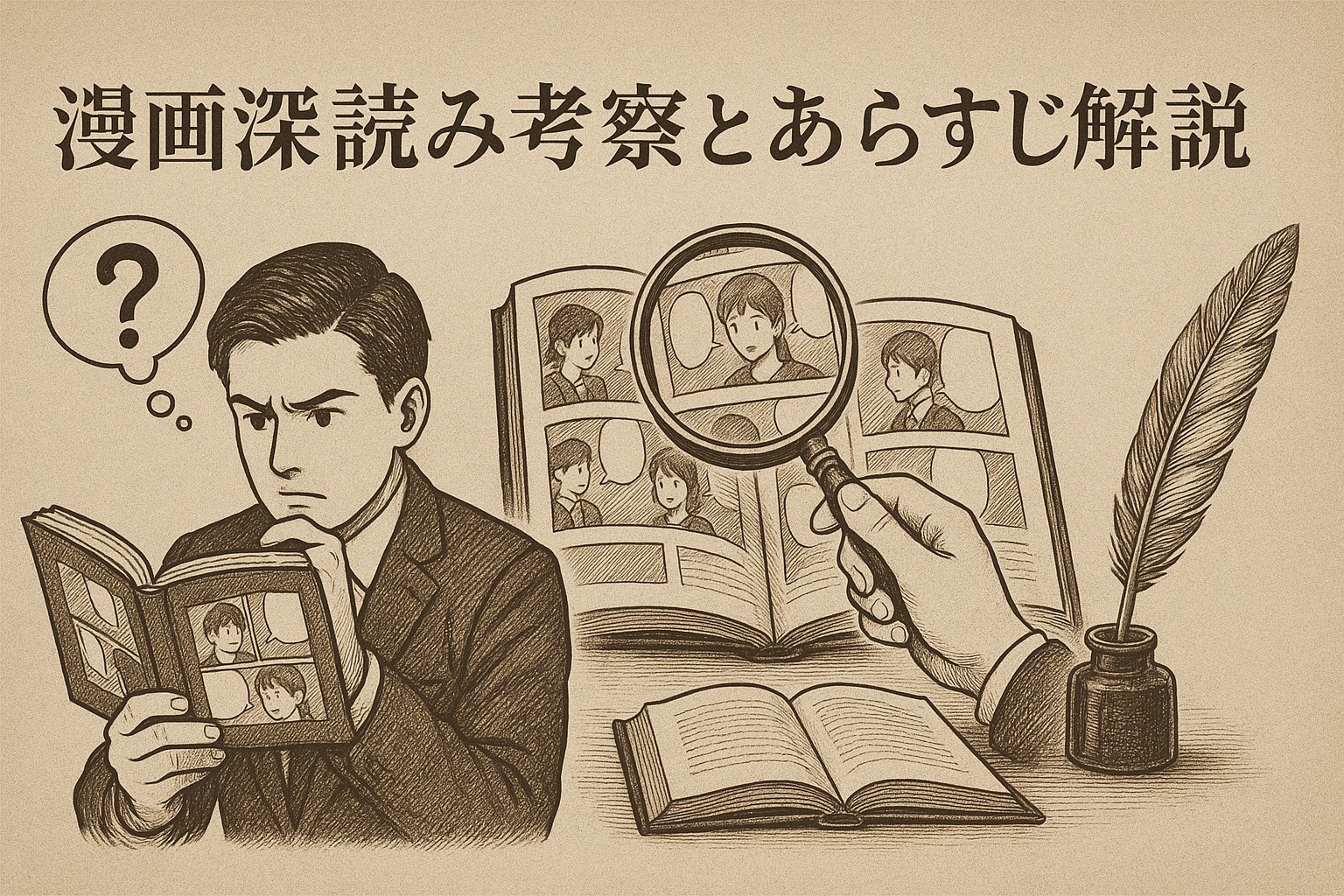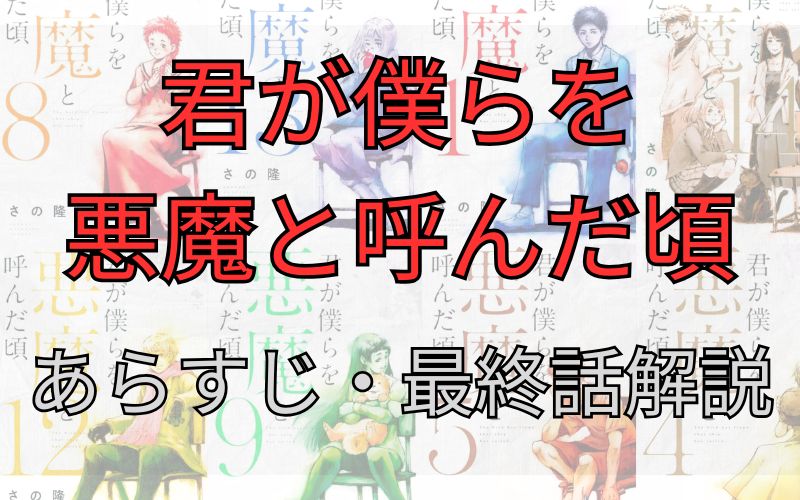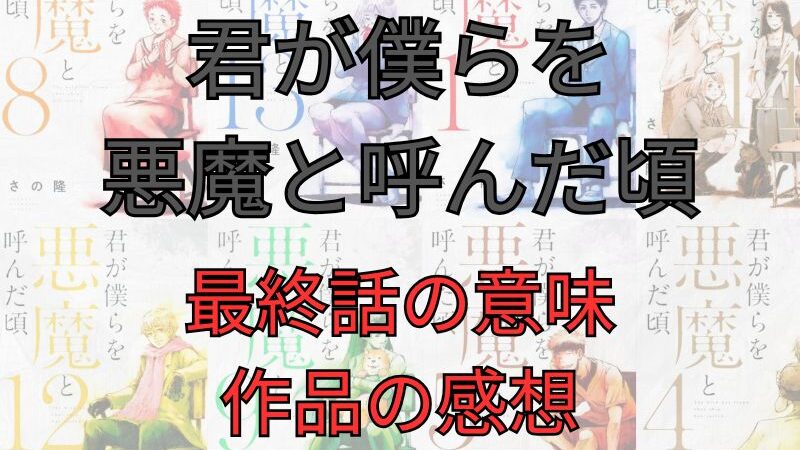
「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」は2017~2020年に『マガジンポケット』に連載されていた人気漫画。
ここでは「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」の最終回の意味・全編を読んでの感想を語っていきます。
| 初版発行日 | 2018年3月9日発売 |
| 掲載誌 | マガジンポケット |
| 出版社 | 講談社 |
| 作者 | さの隆 |
| 巻数 | 全14巻(コミックス) |
| ジャンル | サスペンス |
| Wikipedia | 「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」のWikipediaはなし |
「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」最終回
「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」の全編あらすじは以下によって解説をしているので、気になる方はご参考に。
学生の頃、非道の限りを尽くして、多くの人間を傷付けて追い込んだ斉藤悠介。
彼は、一ノ瀬明里によって己が犯した非道の数々を認識させられたとき、記憶を失った。
今までの非道な人間とは一変して、穢れのない善人へと変わった悠介。前向きに生きていこうとするが、自分が過去に犯した罪によって、様々な人間から責められることに。
記憶には残っていないものの、自分の犯した罪だと受け入れ、「それでも誰かの役に立ちたい」と懸命に生きる悠介。
信頼を勝ち取っても、過去を暴かれ、迫害を受ける。
そんな人生を送ってきた斉藤悠介は、悪徳刑事である米村正次によって拳銃で撃たれ、28歳にしてその生涯を終えることになる。
短い生涯を終えた悠介だが、彼には1人娘岡崎菫(おかざきすみれ)がいた。
顔も見た事がない父親である悠介がどんな人物だったのかを知りたい菫は、生前深い関わらりがあった人物に「斉藤悠介とはどのような人物だったのか?」と聞いて回ることに。
- 学生時代一緒に悪事を働いた会澤陽二郎。
- 凌辱の限りを尽くしながらも愛し合った一ノ瀬明里
- 記憶を失ったあとに恋愛関係に堕ちた大河原環
- 学生時代に酷いイジメを受けた久保秋
- 義父からの虐待を救った藤森蒼志、藤森茜、藤森緑
- 妹が悠介に救われた恩田夏樹
様々な人間にインタビューを行い、悪魔の部分と善人の部分を認識していく菫。
ある日、画家となった藤森緑が悠介を題材にした個展を開くことに。悠介に関わった全員が個展に参加します。
【以下は最終回のあらすじ】
藤森緑が見ていた悠介。優しくて、穏やかな悠介の表情をみたことで、イジメっ子時代を知る会澤・秋はかつての悠介との違いを受け入れることが出来ず。
明里と環は、善人だった悠介が描かれていたことから涙を流しながら緑に感謝を述べることに。
過去の悪行から、世間では「悪の権化」と捉えられている悠介。
悪事を働いた米村によって殺害された時も、米村を美化するような意見も多く寄せられた。
悠介が過去に行ってきた悪事は決して許されるものではない。悪魔と呼ばれることも、責められることも仕方のないこと。
それでも、悠介は全てを受け入れて誰かの役に立ちたいと思って生きてきた。そして、藤森家の3人、菫の母親岡崎椿など、確実に救ってきた人間はいた。
藤森家の3人は、自分達と悠介の関係を赤裸々に語ってきたが、世間からは「悪魔の仲間」というレッテルを貼られた。
絵を描いた藤森緑は、斉藤悠介を許せない人がいる前提で、自分の考えを伝えます。
完璧な善人がいないように、全くの悪人もいない。人は時に罪を犯し、時に人を救う。わかりやすいレッテルとしての善悪など、本当は存在しない。
緑は漫画を読んでいる読者たちに以下のような問題提起を行います。
あなたの目に「斉藤悠介」の姿はどう映りましたか?
貴方の答えを何一つ否定しない。だから、誰にも左右されない貴方自身の言葉で、あなた自身の答えを教えてください。
緑が語り掛けたあと、斉藤悠介の自画像を描いて作品は終了となります。
「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」最終回の意味
作者から読者に問いかけるという異色の最終回を迎えた「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」。
この問いかけに応える前に、この作品の最終回で訴えていることを整理していきます。
最終回で問われていることは大きく分けて3つ。
問題提起された内容
- 過去に罪を犯した人間はどう生きればいいのか?
- 過去に罪を犯した人間は許されるべきか?
- 罪を犯す人間は特別な存在なのか?
上記3点について、解説していきます。
過去に罪を犯した人間はどう生きればいいのか?
作中の主人公である斉藤悠介。
第2部以降は、誰かの助けになりたいと必死に生きる姿は多くの読者の共感を引きましたが、最初のストーリーを見ると「言葉にできないほどの残虐な行為」を繰り返していました。
改心して必死に生きていく斉藤悠介ですが、過去の悪行を知られたことで迫害を受けることに。
では、悠介はどのように生きたら、幸せに生きていけたのか?
善に切り替えて、生きていくと相手から責められてしまうのであれば、いっそ悪に染まった方が幸せに生きていけたのか?
いや、いっそのこと自殺をすれば、誰にも不快な想いをさせなかったかもしれない。刑務所に一生ぶち込まれれば、世間は安心してくれたのかもしれない。
過去に大きな悪行を重ねてしまった人間は、その後どのように生きていけばいいのか?(死んでしまった方が良いのか?)
そういったテーマについて問われています。
過去に罪を犯した人間は許されるべきか?
斉藤悠介は多くの人達を傷付けてきました。
あまりにも残虐な行為だったので、傷つけられた人たちの中には二度と立ち直れない人もいるでしょう。
人の人生をめちゃくちゃにしてしまった人間は許されるべきなのか?
これが、最終回で問われている2つ目のテーマです。
「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」は漫画なので、記憶喪失という手段を使って、「100%の悪から100%の善へ」というパラダイムシフトが分かりやすく描いていました。
悪事を犯した人間が、機械のようにスイッチをオンにして、100%善人として生きていけるのであれば世間の見る目も変わると思いますが、現実の人間は違います。
大きな悪事を犯した人間が、頑張って半分は善の要素を取り入れて更生した。
このような場合、世間は許すべきなのか?迫害をしてしまうことは仕方がないことなのか?加害者の人権は尊重されるべきなのか?
悪事を犯す人間の方が少ない現実を見ると、読者にとってはこのテーマが強く問われているように思えます。
罪を犯す人間は特別な存在なのか?
斉藤悠介は理由なく、残虐な罪を犯してきました。
作品の序盤を見ると、ここまで酷いことをする人間は滅多におらず、斉藤悠介は特別な存在だという印象を持ってしまいます。
ただ、世の中には斉藤悠介が行ったような暴力・イジメ・レイプ・虐待等の暴力を至る所で行われています。
これらを行う人達は「選ばれし狂人」なのか?罪を犯す人間は特別な存在なのか?
上記のような点についても問題提起されています。
私が今まで生きてきたなかで、見てきた風景を思い返すと…。
- 小学生時代に容姿を揶揄したイジメがあった。
- ガキ大将的な存在の子供が暴力を振るっていた。
- 職場で成績を出さない社員に対して暴力が振るわれていた。
- アルコールを飲めない人間に対して強制的な摂取を促した。
- 職場でも陰湿なイジメが行われていた。
- 家庭内でも配偶者にいうことを聞かせるため刃物で脅迫をした。
上記は、私が見てきた一部ではありますが、こんなことがありました。
上記のようなことを行う人間と斉藤悠介は違う人間なのか?また、意図した行動出なかったとしても人間は人間を傷付けているもの。
私も多くの人間を傷付け・傷付けられたことで今に至っている訳ですが、斉藤悠介のような目立つ存在だけを「悪」と定義することは正しい認識なのか?
こういった点も問われていると考えるべきでしょう。
「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」を読んでの感想
あなたの目に「斉藤悠介」の姿はどう映ったのか?
作者であるさの隆さんから問題提起を頂き、最終回で問われている内容についても洗い出したので、私なりの回答を書いていきたいと思います。
最終回を読んだ感想
- 人間の心はグラデーション。
- 過去に犯した罪は一生消えない。
- 人は変わることが出来る。
- 自分を受け入れてくれる人は必ずいる。
- 生きていくために環境を変えるべし。
1つずつ私の感想を語っていきます。
人間の善悪はグラデーション
学生時代は残虐の限りを尽くした斉藤悠介。
どこからどうみても100%の悪人という描かれ方をしていますが、現実的に100%の善人・100%の悪人はいません。
誰の心の中にも白いものと黒いものが混在しており、場面によって白が出たり・黒が出たり、白が大きくなったり・黒が大きくなったりするものです。
つまり、罪を犯す人間は特別ではないということ。
家族内での殺人事件などが報じられることがありますが、その理由は「介護疲れ」であったり、「普段から抑圧されて追い詰められたり」というようなものが多く見受けられます。
介護をすることがなく、穏やかに生活が出来ていれば殺人には至らなかったでしょうし、抑圧されることなく個性を尊重してくれれば、殺人には至らなかったでしょう。
悪辣な環境・状況に追い込まれたことによって、自身の中にあった「黒の部分」を大きく膨らませることになってしまった。
10%だった黒の部分が、90%まで上昇したとき、人は凶行に及ぶ可能性があります。
人間の心は機械のようにスイッチのオンオフが利かないので、誰しもが犯罪者になる可能性があるし、誰しもが幸せに暮らせる可能性はあります。
過去に犯した罪は一生消えない
斉藤悠介は改心してからも、過去のことを持ち出されて攻め続けられましたが、過去に犯した罪は一生消えないのは仕方のないところ。
なぜなら時間は戻せないですから…。
こことは向き合って生きていく他ありません。
よく「学生時代には、暴走族・ヤンキーをやっていて、社会人になったら更生した」というエピソードが美談化されることがありますが、個人的には疑問を感じています。
暴れていた時に被害を受けた人間はいるはずですから、「過去の事だから知らね」というスタンスは都合が良すぎるように感じます。
ただ、時間は戻せないため、それらを全て元に戻すことも出来ません。つまり、過去の罪と向き合うことは、「過去のことを踏まえて、今を誠実に生きること」なのだろうと思います。
斉藤悠介は過去に犯した罪を認識して、今を誠実に生きようと精一杯努力をしました。
直接被害を受けた人が許せないのは仕方ないですし、許す必要はないと思いますが、私は身近に斉藤悠介がいたら許します。
もちろん、「また何かをするのではないか?」と不安に思う周囲の住民の意見も分かりますが、その不安な気持ちを暴力や迫害で表したら、罪を犯す側に変貌してしまうのではないでしょうか。
悠介を危険視するなら、静かに悠介から離れていく。これが取るべきリアクションだと感じます。
人は変わることが出来る
「人間は自分が変わろうとすれば、変わることが出来る」。そう思っています。
斉藤悠介は記憶喪失になって人格が一変しましたが、実際にはそんな都合のいいことは起こりません。
変える方法は、「自分の醜い部分を認めて、その醜い部分を変えようと決めて、様々な考え方を吸収。吸収した考え方を実践して、トライ&エラーを繰り返しつつ変えていく」という地道な方法のみ。
その際に最も重要なのは『人のせいにしない』ということ。
他責思考は”自分が変わらずに人を変えさせよう”という発想。人のせいにすることは楽な行為なので、なかなか抜け出しづらいですが、ここを抜け出せば自分を変えることも可能です。
一つ誤解を避けるのであれば、自責思考は「自分が悪い」と決めつけることではないということです。
自分を卑下して、自分が悪いと思うのではなく、「周りの状況に対して自分がどう対処すればいいのか?」を考えるという意味になります。
自分が人を傷つけてしまったのであれば、自分はどうあれば、人を傷つけない行動を取れるのだろうか?
このことを考えることですよね。あいつがこう行動しなかったせいだと思うのではなく、自分を変える事が出来るようになります。
常にフォーカスを自分に向けることは重要な要素ですね。
自分を受け入れてくれる人は必ずいる
斉藤悠介には、藤森家や岡崎椿などがいたように、どんな人でも自分を受け入れてくれる人は必ずいます。
大きな罪を犯せば犯すほど、受け入れてくれる人は減るかもしれません。ただ、それでも自分を受け入れてくれる人はいる。
私も数十年生きてきて、辛い思いをすることはありましたし、「こいつは敵だ」と思う人もたくさんいました。それでも、自分を受け入れてくれる人が出てくるんですよね。
そのためには多くの人と接することが必要。
世の中に100%はないので、一発一中を実現させる事は無理ゲー。目の前の人とわかり合うことが出来なかったとしても、違う人とならわかり合うことも出来るかもしれません。
斉藤悠介にも分かってくれる人が出来たように、どれだけ罪深いことをしても分かってくれる人はいるはずです。
生きていくために環境を変えるべし
人間は生きていく環境によって、大きく影響される生き物。
仕事もいい環境でやれば、パフォーマンスが変わるのと同じように、より良い自分として生きていくためには、良い環境を整えることがとても大切になります。
斉藤悠介が最もしくじったのはこの点にあると言えます。
自分の事を知る人がいない土地を求めて、田舎を拠点にして生活をしていたのですが、基本的に田舎は閉鎖的。
人のゴシップが激しく行きかう場所で、強い監視社会。
私の友人は、「昨日の12時に外出していたけど、どこへ行っていたの?」とか「ずっと車が停まっていたけど、仕事には行ったの?」という声を掛けられて、唖然とした経験があるそう。
日本は島国でムラ社会の傾向が強い傾向にあるため、よく言えば連帯感を生む行動・悪く言えば他人を縛り付ける行動を起こします。
悠介は大きな都市から少しだけ離れたエリアに住めば、ここまで他人のゴシップを掴もうとする人たちはいなかったでしょう。
悠介の過去を暴こうとする人物もいなかったし、過去を知っても積極的に絡んでくる人もいなかった。
自分にとって快適な環境で生きていく為には、住む場所などの環境を探ることは大切ですね。
まとめ
ここまで「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」の最終回の意味と全編を読んでの感想を話しました。
斉藤悠介の中学校時代の悪行を考えると、「生きている価値無し」と言いたくなります。
しかし、このストーリーをもう少し薄めて、自分達に投影してみると、過去に自分が犯してしまった失態・その失態を基にどのように生きていけばいいのか?
ということを考えることが出来る感慨深い漫画であると言えます。
1巻だけ読んで離脱してしまった人もいるでしょう。しかし、そこを乗り越えて読み進めて貰えば、違う視点での面白みがあるので、是非再度チャレンジしてみてください。